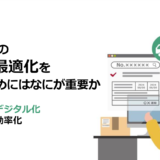物流現場のデジタル化は、もはや避けては通れない経営課題となっています。特に人手不足や物流2024年問題、コスト増大など、様々な課題に直面する中、業務改善とデジタル技術の活用が注目されています。本記事では、物流改善における実践的なアプローチから具体的な実装方法まで解説します。
物流業界を取り巻く構造的課題とデジタル化の必要性
物流業界は深刻な人手不足やコスト増大など、様々な課題に直面しています。これらの課題に対して、従来の人手による対応では限界があり、デジタル技術を活用した抜本的な改革が必要とされています。ここでは、業界が抱える構造的な問題と、デジタル化による解決の必要性について解説します。
現場が直面する課題
物流現場では、人材不足が最も深刻な課題となっています。国土交通省や鉄道貨物協会の調査によると、2028年度までにトラックドライバーだけで約28万人が不足する見込みです。この人材不足に加え、2024年4月からの労働時間上限規制により、デジタル技術を活用した業務効率化が不可欠となっています。
さらに、時間指定配送や温度管理など、顧客ニーズの高度化も課題となっています。これらの要求に対して、人手のみでの対応は困難になってきており、IoTセンサーやリアルタイムモニタリングなどのデジタル技術の活用が求められています。
※経済産業省・国土交通省・農林水産省:「我が国の物流を取り巻く現状と取組状況」(https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/sustainable_logistics/pdf/001_02_00.pdf )
物流コストの構造的課題
コスト面でも深刻な課題が山積しています。最低賃金の上昇と人手不足による人件費の増加は、自動化・効率化による抑制が必要となっています。また、国際情勢による燃料費の高騰に対しては、配送計画の最適化やデータ活用による効率化が求められています。
特に大きな課題となっているのが、EC市場の拡大に伴う小口配送の増加です。これにより配送効率が低下し、コスト増加につながっています。この課題に対しては、デジタル技術による配送の効率化や、配送ルートの最適化が有効な解決策となります。
このように、物流業界が直面する課題は多岐にわたり、その解決にはデジタル技術の活用が不可欠です。
物流2024年問題について詳しくは、「物流クライシスとは?物流DXで2024年問題から脱却するには」をご覧ください。
物流業務における効率化のアプローチ
物流現場の効率化を実現するには、現場改善とデジタル技術の活用をバランスよく進めることが重要です。効率化アプローチは大きく2つに分かれており、まずは基本的な業務改善から着手し、その上でデジタル技術を効果的に組み合わせていくことで、より大きな成果を得ることができます。
基本的な業務改善
- 入出荷作業の効率化
動線分析に基づく作業エリアの最適化と手順書の整備により、作業の標準化と生産性向上を実現します。これにより人的ミスの低減と作業品質の安定化も期待できます。
- 在庫管理の最適化
データ分析に基づく需要予測により、過剰在庫の削減と欠品防止を両立します。季節変動や特需にも柔軟に対応できる在庫計画の立案が可能になります。
- 配送計画の改善
配送時間帯の分散化とエリアの最適化により、車両の稼働率を向上させます。エリアごとの需要変動を考慮した効率的な配車計画を実現します。
デジタル技術の活用
- システム連携や自動化ツール導入による効率化
受発注システムと基幹システムの連携や、自動化ツールの利用を検討します。受発注情報の入力の手間が省けるだけでなく、自動化することでより正確・迅速に業務を遂行できます。
- データ活用による最適化
BI(ビジネスインテリジェンス)ツールやデータ分析プラットフォームを活用し、作業時間の分析やエリアごとの配送効率の比較・検証を行います。リアルタイムなデータをAIで分析し、改善ポイントを特定することで、数値に基づく計画的な改善活動の展開が可能になります。
- モバイル機器の活用
ハンディターミナルやタブレットによる現場でのリアルタイムなデータ更新により、在庫精度を向上させます。事務所での入力作業の削減と情報共有の迅速化を実現します。
物流業務(発送業務)の課題や解決については、以下の記事で詳しく解説しています。
「物流業界の課題―業界を取り巻く社会の変化と課題解決に向けたDXの実現」 「RPAで物流業界を効率化!進化する物流テック」
デジタル化による改善の実践ステップ
デジタル技術の活用は、物流改善において大きな効果が期待できます。しかし、その導入には慎重なステップを踏む必要があります。システムの選定から現場への定着まで、多くの企業が試行錯誤を重ねているのが現状です。ここでは、効果的な改善を実現するための段階的なアプローチと、具体的な実行計画について解説します。
Step1:導入準備フェーズ
- 業務プロセスの可視化
作業時間の測定と現場の意見聴取により、改善が必要な領域を特定します。作業フローの分析を通じて、効率化の余地がある工程を明確にします。
- 改善余地の検討
手作業による入力業務や定型的な作業を分析し、自動化による効果が高い領域を見極めます。作業負荷の大きい工程から優先的に改善を検討します。
- 投資対効果の試算
人件費の削減や作業時間の短縮など、具体的な数値目標を設定します。導入コストと期待される効果を比較し、投資判断の基準を明確にします。
Step2:システム導入フェーズ
- システム要件の定義
業務要件の整理と最適なシステムの選定を行います。現場の要望を反映しながら、将来的な拡張性も考慮したシステム設計を実施します。
- パイロット導入
特定エリアでの試験的実施により課題を洗い出します。小規模な範囲での検証を通じて、本格展開時のリスクを最小限に抑える準備を進めます。
- 本格展開
効果検証を踏まえた全社展開を推進します。パイロット導入での学びを活かし、段階的な展開計画を立案して確実な定着を図ります。
Step3:運用定着フェーズ
- 現場教育の実施
操作研修と業務ルールの徹底を図ります。マニュアルの整備と定期的な研修により、誰もが同じレベルで運用できる体制を構築します。
- 効果測定の仕組化
定量的な効果把握と改善点の特定を行います。KPIの設定と定期的なモニタリングにより、継続的な改善活動の基盤を確立します。
- 継続的な改善
運用ノウハウの蓄積と展開を進めます。現場からの改善提案を積極的に取り入れ、システムの活用レベルを段階的に向上させます。
物流センターにおける効率化の成功事例を集めた事例集を無料でご提供いたします。必要な方は、下記よりダウンロードしていただけます。
「物流センターの課題解決事例集~発送の最適化と帳票処理の効率化」
効果的な改善を実現するための実践ポイント
物流改善を効果的に進めるためには、組織的な推進体制の構築と、具体的な成功事例からの学びが重要です。ここでは、改善活動を成功に導くための実践的なポイントと、実際の企業における改善事例を紹介します。
推進体制の構築
- 経営層のコミットメント
改善活動の成功には、経営層による適切な理解と支援が不可欠です。予算や人員配置において、必要なリソースを適切なタイミングで提供することが重要です。一方で、経営層の関与が形式的になりがちなため、定期的な進捗確認の機会を設定し、現場の課題や要望を直接把握する仕組みを構築する必要があります。
- 現場との協力体制
現場スタッフの積極的な参画は、改善活動の成否を決める重要な要素です。現場の知見を活かした改善策の立案により、実践的で効果の高い改善が可能になります。しかし、新しい取り組みへの不安から反発も予想されるため、目的や効果を丁寧に説明し、段階的な展開を行うことが重要です。
- 部門横断的な推進
物流改善の効果を最大化するには、物流部門だけでなく、営業部門や生産部門を含めた全社的な取り組みが必要です。部門間の連携により、サプライチェーン全体の最適化が実現できます。ただし、部門間の調整不足による非効率を防ぐため、定期的な連絡会議の開催など、具体的な連携施策を講じることが重要です。
具体的な改善事例
物流改善を成功に導くためには、他社の取り組みから学ぶことが有効です。作業自動化、設備導入、システム統合の3つの異なるアプローチで成果を上げた事例と、それぞれの成功のポイントを紹介します。
- 作業自動化による改善: [アパレル企業B社]
B社では、商品の入荷・出荷時に手作業での検品が必要でしたが、その作業は店舗のPOSシステムとは連携していませんでした。そこでRFIDタグを活用し、入荷時から出荷時までの一括管理を実現。その結果、検品作業の時間を2/3に、棚卸しの時間は1/4に短縮することに成功しました。同時にPOSシステムとの連携により、在庫データのリアルタイム把握が可能となり、発注精度の向上にもつながっています。
- 設備導入による改善: [C社(製造会社)の事例]
製造会社C社では、従来はハンドリフトを利用し人力で物を移動させていたため、運べる荷物の量や重さに限界がありました。また、バランスを崩して荷崩れを起こし部品を破損したり、スタッフが腰を痛めたりといったことも大きな課題でした。AGVの導入により、スタッフに代わりAGVが運搬を担当。スタッフはピッキングした荷物を置くだけで済み、働きやすい職場になっています。レイアウトや業務フローの大きな変更はせずに、運搬作業において大きな効率化に成功しました。
- システムによる統合的改善: [サーモス社の事例]
サーモス社では、複数の運送会社ごとの対応が必要である煩雑な伝票の作成・発行業務の効率化を、優先して取り組むべき課題と位置付けていました。受注の際にデータ入力に多くの時間を費やすことに加え、手書きで送り状に個数・重量などの記載をしていたのです。そこで、運送EDI対応の送り状・荷札発行システムを導入。それまで運送会社ごとに複雑な手作業が発生していた工程に、1人のオペレーターによるPC入力のみで対応することが可能となりました。その結果、事務所での送り状発行工程を10工程から4工程に、出荷現場での工程も5工程から4工程に削減し、大きな業務効率化を実現しています。
送り状作成・発行における課題やデジタル化による改善は、下記の事例をご覧ください。
「送り状の貼り間違いや出荷問い合わせで物流現場は混乱。「送り状を発行しない」しくみで解決」
「送り状発行から出荷実績報告までを自動化。問合せ対応工数の大幅削減を実現」
持続可能な物流改善に向けて
物流業界を取り巻く環境は、労働力不足や品質要求の高度化など、年々厳しさを増しています。このような状況下で企業の競争力を維持・向上させるには、現場改善とデジタル化による業務改革が不可欠です。
改善の推進には、自社の現状と課題を正確に把握し、投資規模に応じた適切なアプローチを選択することが重要です。また、単なるシステム導入に留まらず、組織体制の整備や人材育成を含めた総合的な取り組みとして進めることで、より大きな成果を得ることができます。
特に発送業務においては、複数の運送会社との連携や送り状発行作業の効率化など、早期に着手できる改善ポイントが多く存在します。ユーザックシステムでは、このような物流現場の課題に対応する「送り状名人」をはじめとした各種ソリューションを提供しています。まずは身近な業務から改善を始め、段階的にデジタル化を進めていくことで、持続可能な物流改革を実現することができます。
また、発送業務のデジタル化による業務効率化について、わかりやすくまとめた資料をご提供しています。下記より無料でダウンロードしていただけますので、ぜひご活用ください。